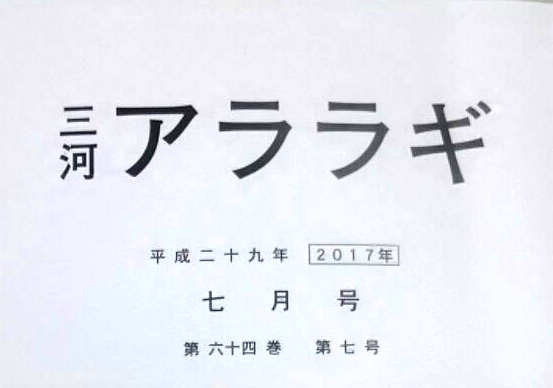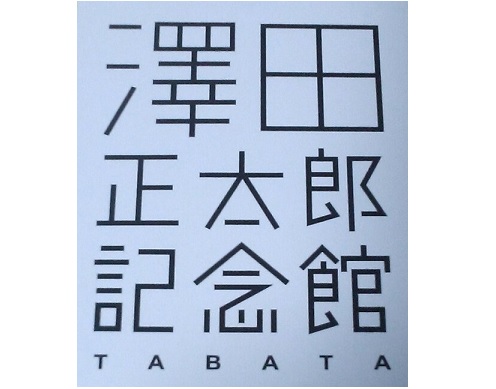最近、読み聞かせ、それも文字を習う前の小さな子を対象としない、大人の読み聞かせを体験する機会があった。大人を対象にするので、朗読やちょっとした江戸時代の小話を聴く、みじかい落語の感じがした。このような体験の延長で声優さんのいろいろな作品を朗読しているYoutubeを検索・視聴し、そんなことを暇に任せてお盆休み前にしていたら、芥川龍之介の作品は短編が多いので、結構、朗読対象になっていたことを知った。これまで、長編作品のたけくらべなど難解な樋口一葉の作品に挑戦し、そのままになっていた。今年のお盆前には芥川の羅生門の朗読を始めとして、蜘蛛の糸を繰り返し繰り返し、聴き惚れてしまった。
そして、六九歳になって初めて知ることになる「白」という短編作品がYoutubeのトップページを飾っており、それは淡いグレーと濃いグレーの単調2段階でデザインされて、特徴の無い犬が淡いグレーで描かれており、ははーん、これで<しろ>という犬の話になるのだなと思ってしまった。以降、私はその朗読を聴いた「白」の感想を呟くつもりはなく、詳しくは文字で全貌が紹介されている青空文庫などを参照して頂きたい。
さて、子供の絵本の読み聞かせ会などがあるが、文字をまだ知らない小さな子は絵本で与えられているカラフルな絵柄という作家特有な映像と耳から得た聞きことば情報を的確に覚え、自分の頭に刻み込んでいるのだ。諳んじている自分の知っている絵本の内容を早くお披露目したく、我が家では子供がまだ小さい時、家内が絵本を読み始めると長男がまだそこまで進んでいないストーリーを弟・妹にばらしてしまい、よく小さな喧嘩の始まりとなった。
大人の読み聞かせには例として初めて聞く作品の朗読が一番だと思う。初めて聴く新鮮な言葉を受け入れ、それを瞬時に同期させ、こんな情景なんだろなとか、思い浮かべる自らが創造する色合いの情景は私には楽しい。個人個人によって情景の配置や色合いは異なって当たり前であろう。しかし、著名な作品が映画化、TVドラマ化され、さらにヒットしてしまうと自分で想像するという前に監督だのドラマ演出家の意図が前面に出て、作品の著者が意図していない方向へどんどん行ってしまう事もあろうが、そういう時は小さな諦めも必要だ。
私は初めての「白」から1週間ほどして、2度目の<しろ>を探した。というのは、芥川は結婚9年目で自殺してしまったが、その4年前の結婚5年目にして自殺を暗示させる作品を残そうとしていたのかと背筋が本当にゾッとした。隣のくろと呼ばれる黒い犬が犬殺しに捕まり、自分は咄嗟に逃げ、自分だけ生き残った事を苛み、「白の中で1度だけ自殺したいということばが出てきた。
実は<しろ>は外観が黒い犬「芥川は鍋底よりも黒いと表現している」に変わってしまい、田端の駅付近から流浪の旅に出るのだが、出来れば死にたい死にたいと、あちこちで、蛇や狼と戦い、火や鉄道に飛び込み子供を助け、アルプスの山では遭難しかけた一高生を助け、死にきれずに自宅に戻るのある。その流浪の旅は決してカラフルでなく、ほとんど白黒の世界に近かった。
数年前、私は芥川が世間で言われている神経衰弱で病み、藤沢の鵠沼の海岸近くで療養し、自殺する前に東京田端の自宅との間を行き来した時期について調べた。新婚生活を始めた鎌倉にも近い鵠沼、その後田端の自宅に戻っても二階に籠り文章を練る作業に没頭し、神経衰弱の源は自分の作品なのか、それとも別なものなのかと、さらに健康もすぐれずにいたという。鎌倉や鵠沼と聞くと自然豊かな、新緑の緑を表現する場合や碧い海と連なる同じくあおい空を表現する場合には、組み合わせや、グラデーションまで考えると数え切れないわくわくする空間を想像し、そんな色合いが豊富な世界・暮らし向きを勝手に考えてしまうが、実はそうでなかった芥川の白黒の濃淡の世界が支配していたのだろうと想った。
朗読を拝聴し、自らは書かれた文字を目線で追う作業の代りに(といより軽減し)、余裕を持って色とは別の次元の世界の探索、つまり書き手の気持ち、意図、精神状況、心理状態等々を想像・推測出来ると信じている。<しろ>は人の話していることは分かっている。しかし、人は<しろ>の言葉は分かっていないという。「白」では精々茶色い世界までしか覗けず、それでも裕福だと思い詰めている。<しろ>が何とか自分の家に戻って来るが外観が黒く汚れているので、坊ちゃん・お嬢ちゃんには分かってもらえず、手荒く・ぞんざいに扱われてしまう状況に落ち込んでしまった。
よく、漱石の話で出てくる I love you を月が綺麗ですねと訳せる心持と、どうしても引用させて頂きたいのだが、芥川と結婚が決まっていた文はお相手のお名前は聞かれても言い出せずに、そっと羅生門の冊子を差し上げたという逸話を最近知ることになって、芥川も文さん位のある種の心持の余裕があればもっと長い結婚生活をおくれたのではないかと思った次第です。
白:芥川龍之介の短編に接して
 滝野川界隈のひと
滝野川界隈のひと